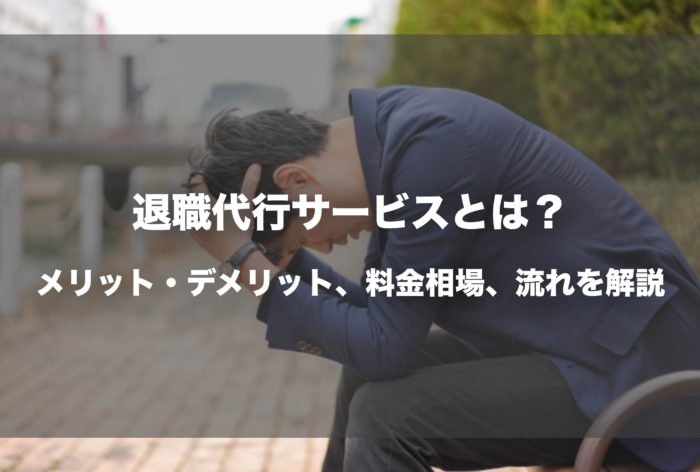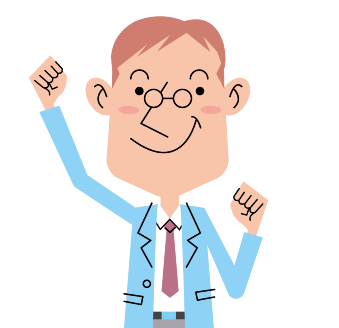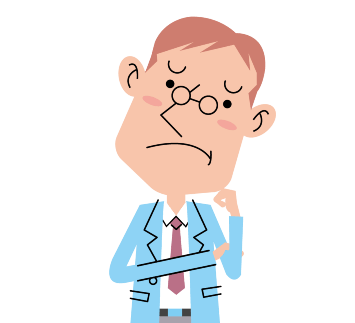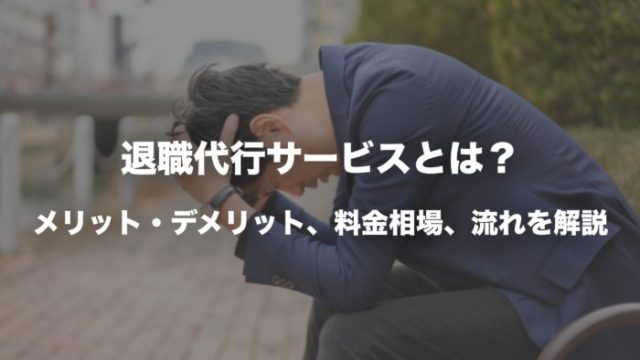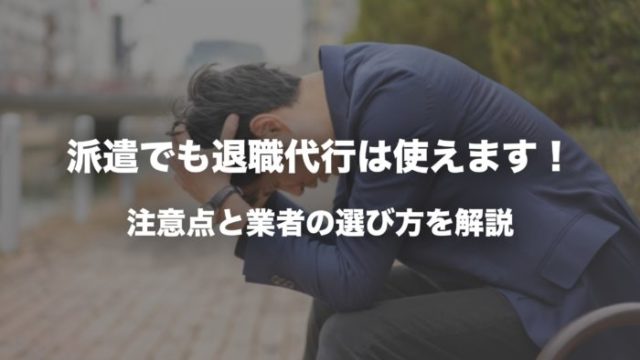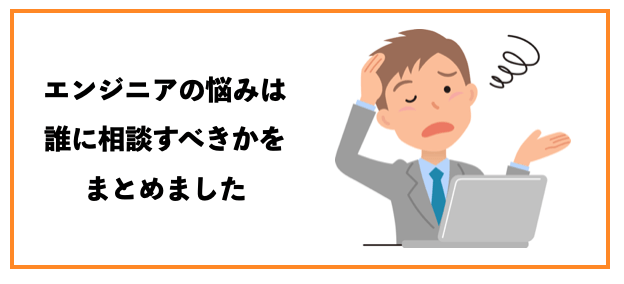20代、30代での転職が当たり前になり、新卒採用の社員も、3人に1人が入社後4年未満で辞めてしまう時代です。
しかし退職が当たり前になったとは言え、派遣契約や、SES(客先常駐)で働くエンジニアのみなさんにとって、退職を申し出る心理的なハードルは高いのではないでしょうか?
『引き継ぎが必要だから、交代要員が準備できるまで一年待ってほしいと言われた』
『上司や営業との面談で、長時間拘束されそうで気が滅入る』
『派遣契約の満了日まで3ヶ月もあるが、耐えられない』
みなさんが退職を切り出せば、顧客との契約期間、会社の都合、プロジェクトの都合、、、、等々、関係者が自分の都合を言い始めることが予想できます。
こんなことは、契約との間で板挟みになっている、派遣・常駐エンジニア特有の状況です。
このため、近年では「退職代行サービス」を利用して、えいやっと退職してしまうエンジニアの方を見かけるのは普通のことになってきました。
会社を直ぐにやめたいのにやめることができない方のために、あなたに代わって会社に対して退職の意思を伝え、必要な手続きまで行なってくれる「退職代行サービス」。
退職代行サービス自体は聞いたことがあるという方が多いかと思いますが、この機会にエンジニア目線で解説します。
退職代行とはどのようなサービスなのか?
退職代行サービスとは、会社を退職したいと考えている労働者にかわって、退職の意向を会社に伝えてくれるサービスです。
人材不足の影響もあり、執拗な退職の引き留めにあい、会社を退職したくとも退職できない人が増えています。
なかには、退職したいと伝えると、「こんなに忙しいのに退職するなんて、身勝手だ!」と怒鳴られたりするなど、ハラスメントを受ける例もあり、社会問題となっています。
実際に、厚生労働省に寄せられた、自己都合退職に伴うトラブルは、2018年時点ですら4万1258件にも上っています。
このような状況を踏まえ、第三者に退職代行サービスを依頼して、会社を退職する人が増えているのです。
マイナビの調べによれば、2019年に転職した20~50代の男女1500名のうち、【退職代行を利用したことがある、利用したい意向あり】という人の合計は25.7%にも上っています。
退職代行サービスで具体的に行なってくれること
退職代行サービスが具体的に行なってくれることは以下の2点です。
- 依頼者の退職の意向を、退職代行業者が会社に伝えてくれる
- 備品の返却などの連絡事項を会社から聞き、それを依頼者に伝言する。
やってくれること自体は非常に単純なものです。
もともと、労働者には基本的に退職の自由が保障されていますし、退職したい人間を無理やり押さえつけて働かせることも不可能です。
なので、これに応じて即日で退職を受理する会社がほとんどでしょう。
会社として初めての体験だったため、人事部と法務部が労働基準局に細かく確認して対応してくれました。最終的には退職を受理するしかないという結論でした。
退職代行サービスが派遣・常駐エンジニアに支持されている理由
SESだから退職代行使わないと辞めれる気がしない。技術もなければコミュ力もない。社不でごめんなさい。
— 仕事辛い (@TKduvSKLl2RjRKg) February 26, 2021
民法では、雇用期間の定めのない者は2週間前に退職を伝えれば、いつでも退職できるとあります。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法第627条
ですが、派遣・常駐エンジニアの皆さんなら分かる通り、2週間どころか、1〜2ヶ月後の退職ですら不可能に等しい話なはずです。
間違いなく、自社からも、派遣先(常駐先)からも引き留められますよね。
『派遣契約がまだ残ってるでしょ、途中で解約なんてできないよ?』
『交代のメンバーがすぐいないから、お客さんから拒否されるよ。』
『残されたメンバーもお客さんも困るでしょ。仲間を助けると思って、あと半年だけ更新してよ。』
『次の仕事が決まってないのに退職しても、中途半端な奴にいい転職なんて無理だよ。』
正直、これらの引き留め文句を言われても、皆さんは法律や転職のプロではないので何が正しいのか分からないですよね。
想像するだけでも頭が痛くなる引き留め文句ですし、多くの方が「ならば、あと半年だけ頑張ってみます…」と答えてしまいがちです。
こういう状況が容易に想像できてしまうからこそ、
『お客さんとも自社とも揉めたくない』
『あと何ヶ月も働かないと辞められないなんて考えられない』
『担当営業やリーダーと長時間面談になるのが苦痛すぎる』
という理由で、退職代行サービスを利用してしまうのです。
退職代行サービスに申し込むと、依頼された代行業者からは「明日から出社は不要です。電話がかかってきても出る必要はありません。」などと言われます。
事実、多くのケースでその通りになり、問題なく退職できます。
自社としては、執拗に引き留めたことで「ブラック企業だ」などと風評被害に合うことを何より嫌いますし、そもそも突発退職自体がさほど珍しくないのです。
派遣・常駐先としては、もはや泣き寝入りせざるを得ないといったところ。
「退職代行に依頼するくらい追い詰めてしまっていたなんて、申し訳ないことをした」と謝罪されることさえあります。
厳密には派遣契約の解除が必要なことから、契約形態によって対応してくれる業者と対応してくれない業者があります。
詳しい考え方や、派遣契約に強い退職代行業者は「派遣でも退職代行は使えます!注意点と業者の選び方を解説」にて解説しています。あわせてご覧ください!
モラルや社会人のマナーといった観点から見れば、退職代行サービスを使うのは好ましくない行動と思われます。
ですが、自社やプロジェクトの都合で執拗に引き留めたり、自分のスキル以上の能力が求められる仕事にアサインするのは会社として問題です。
自分の性格や健康状態、置かれている状況によって、退職代行を使うのがいいのか悪いのかは変わってくるということです。
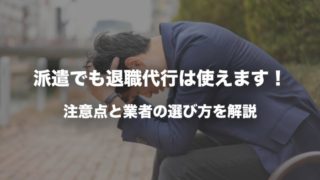
退職代行サービスを利用するメリット
- 自分で言い出せない心理的ハードルが下がる
- 派遣・常駐エンジニア特有の引き留めに合わずに済む
- 客先の上長や、担当営業に顔を合わさず辞められる
1.自分で言い出せない心理的ハードルが下がる
多くの人は自分で退職を切り出し、会社とよくよく話し合って退職していきますが、退職届を受け取ってもらえない、話し合いが難しいという人もいます。
このような人にとっては、第三者に間に入ってもらい、会社に直接退職の意思を伝えてもらえるだけでも心理的に安心できます。
2.派遣・常駐エンジニア特有の引き留めに合わずに済む
契約期間や引き継ぎの都合を引き合いに出して、長ければ半年〜一年スパンで退職を引き留められてしまうのが派遣エンジニアです。
このような自社の都合やプロジェクトの都合に巻き込まれず、無理だと思ったタイミングで辞められます。
3.客先の上司や担当営業に顔を合わさず辞められる
エンジニア職の方は心優しい真面目な方が多いので、気持ちの上ではきちんと正規の退職交渉をしたいと考えているのではないでしょうか。
筋を通したい一方で、客先の上司と話したり、担当営業やリーダーからの面談で話すこと自体が辛いというのも本音だと思います。
退職代行サービスを申し込むと、業者は人事部に直接退職を伝えますので、会社としてドライに手続きが進んでいきます。
退社することを家族には伝えましたが、まだ上司には言えてないです…
理論武装しないと…また詰められる…
なんで…会社辞めるのに詰められるの…
そら退職代行流行るわ…— ながいひとりごと (@nagaihitorigoto) February 18, 2021
退職代行サービスのデメリット
実は私も、後輩社員に退職代行サービスを使われた経験があります。
その経緯も踏まえて、退職代行サービスには以下のようなデメリットがあると考えています。
- 退職するだけで費用がかかることに違和感を感じる場合がある
- 悪質な退職代行業者に依頼してしまう可能性はゼロではない
- 必ずしも退職できるわけではない

1.退職するだけで費用がかかることに違和感を感じる場合がある
退職代行サービスの費用は、1.5〜4万円程度であることが多いです。
普通に自分で退職手続きをしたら費用はタダなので、そんなにかかるの?という人もいます。
退職代行に万単位の金額を払うこととに違和感を感じる程度なら、自分で退職を申し出ればいいだけの話です。
金額面の高さについては、退職代行業者としては基本企業から良い反応はされないですし、怒鳴られたりややこしい話になったりすることが日常茶飯事です。
そういった交渉を収められる精神的にタフな担当者を採用しなければならないからこそ、相応の費用がかかるのです。
2.悪質な退職代行業者に依頼してしまう可能性はゼロではない
退職代行サービスを行う業者の中には、費用を取るだけとって、仕事をきちんと行ってくれない悪徳業者も存在します。
例えば、自分たちの責任の範疇を超えるような回答を会社側がしてきたときに、「自分たちでは手に負えないので、依頼主さんが直接話す必要があります」と言ってくるのが最悪のケースです。(稀ですが、あります。)
退職代行サービスは、何らかの資格が必要なわけではないため、誰でも退職代行サービスの看板を掲げることができてしまうのです。
しかし、どの退職代行サービスの業者が悪徳なのか、見極めが難しいのが現状です。
退職代行の料金は1.5万円~4万円が相場
2021年時点において、退職を依頼する場合の料金は1.5~4万円程度が相場のようです。
数年前にテレビや雑誌で退職代行サービスが取り上げられたことをきっかけに、業者が乱立状態にあり徐々に値下がってきている傾向にはあります。
後払いや分割払いに対応したサービスも出つつあり、業者への信頼度合いと支払い能力とのバランスで選べるようになってきています。
退職代行を使ったけど
所長からの電話に出てしまいお話する事に
お前の行動力好きやでと褒められたけどもう遅いのよ(´•ω•`)本当に嫌なのは直属の上司だし
その人は2つ上だから話できる
退職代行にかかったお金29,800円みんな安いと思う?
高いと思う人は恵まれた職場にいると思うよ
— ふっちー (@fuchi_aslot_329) April 8, 2019
退職代行の基本的な流れ
どの退職代行サービスも、基本的な流れは以下の通りに進みます。
- 退職代行サービスに相談する
- 担当者からサービス内容や費用の説明を受ける
- 正式に依頼をする
- 費用を支払う
- 退職代行サービスの担当者が会社へ連絡を行う
- 退職代行サービスの担当者から退職了承の報告を受ける
- 返却物を会社に郵送する(社員証、社用携帯など)
即日希望、会社と連絡とりたくない、有休を消化したい、離職票・所持品を送ってもらいたいなどの希望は、申込後の相談の場で聞かれることが多いです。
気持ちに余裕があれば、簡単でいいので「業務引継書」をメモ書き程度でも用意しておくと良いでしょう。
主な退職代行サービス業者
「退職まで一歩勇気が踏み出せない」
トラブルがあったり、そうでなくてもモヤモヤした気持ちを抱えたまま退職するのは辛いですよね。
そんなあなたでも安心できる、優良な退職代行業者を5社紹介します。
弁護士監修や、労働組合が運営する業者なので、退職代行サービスを業者に依頼するときに参考にしてくださいね。
- 退職代行Jobs|法令遵守を徹底している安心感
- 男の退職代行|月額3,630円から依頼可能
- 退職代行クラウド エンマン|弁護士による退職代行
1.退職代行Jobs|法令順守を徹底している安心感

「退職代行Jobs」は、顧問弁護士監修で適法適正に厳格な、安心の退職代行サービスです。
労働組合とも連携しているため、もし退職日や有休消化に関して会社と交渉が必要になったとしても問題なく交渉可能で安心です。
24時間365日、即日即時対応可能なのが魅力。
料金は依頼者の雇用形態を問わず一律税込み29,800円で、料金は退職完了後に後払いすることも可能ということで信頼感があります。
2.男の退職代行|男性人気No1、月額3,630円から依頼可能
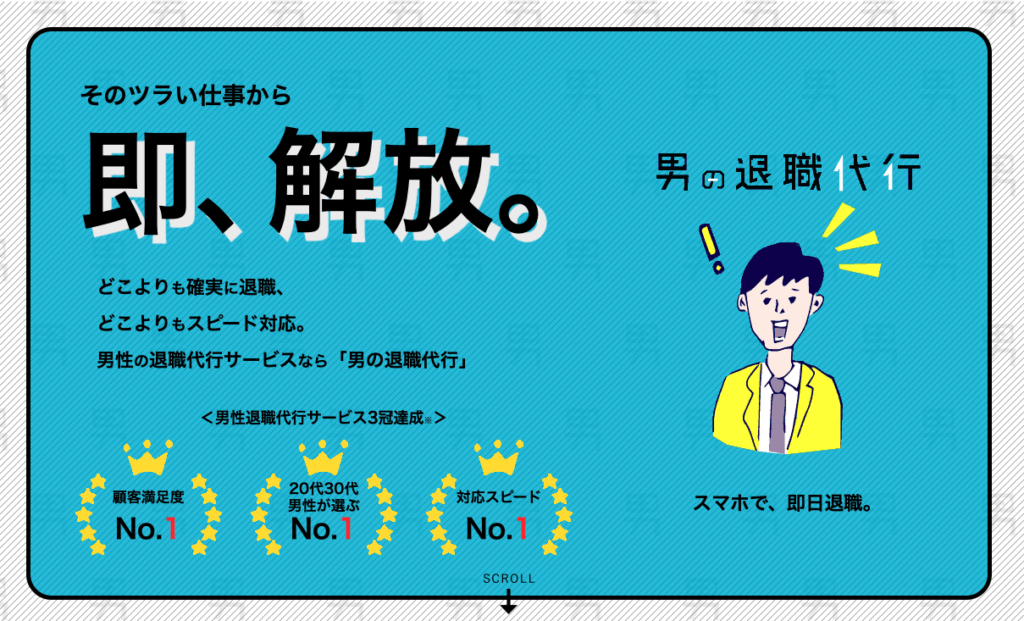
「男の退職代行」は、株式会社インクルが運営する男性向け退職代行サービスです
ユニークな名称のサービスですが、JRAA(日本退職代行協会)にて優良事業者であることを証明する「特級認定」を取得している、真面目な代行サービスです。
法的に認められた労働組合が退職代行サービスを行うため違法性の心配もなく、安心して依頼することができます。
通常料金は29,800円と相場並みですが、「月額3,630円で、1年間に2回まで利用可能なサブスク契約」という、非常に特徴的な料金プランがあります。
実質的には分割払いとして考えればいいので、新入社員や第二新卒のような経済的に厳しい方にはありがたいサービス形態でしょう。
3.退職代行クラウド エンマン|弁護士による退職代行

「退職クラウド”エンマン”」は、紹介している3サービス中で唯一、弁護士が代行して交渉してくれるサービスです。
信頼できる退職代行サービスでは弁護士が監修・指導しているものですが、エンマンについては弁護士自らが代行を請け負ってくれます。
万が一にも会社側が強固に拒んだり、本人との接触を図ろうとしてきた場合にも、弁護士自らが交渉を行なってくれているので安心感が違います。
ただし、料金は税込み55,000円と高めの設定なのが厳しい点です。
(追記:退職が多い時期ということもあり、期間限定キャンペーンで33,000円での依頼が可能とのこと)
炎上案件に首を突っ込んでいて絶対に直接話したくない方や、有休消化・給料支払いが確実に必要だという方には、安心感を買う意味でエンマンを選ぶとよいでしょう。
退職代行を利用する前に理解、注意しておくべきこと
退職代行サービスをいざ利用する前に、3点だけ理解、注意してもらいたいことがあります。
- 退職を代わりに伝えることはできるが、法的な交渉はできない
- 退職理由はなるべく具体的にしておく
- 退職の手続きのために会社から依頼されたことは迅速に対応する
それぞれ解説していきます。
1.退職を代わりに伝えることはできるが、法的な交渉はできない
今回紹介した「退職代行Jobs」を始めとする退職代行サービスは、弁護士資格を持たない一般事業者です。
みなさんが勤めている会社側に対して、退職代行業者が退職の意思を伝えたり、要望を伝えること自体は違法ではないのですが、法的な交渉ごとはできないのです。(これを法律用語で「非弁行為」と言います。)
具体的に例を挙げて説明しますと、以下のような交渉ができないということです。
- 未払い残業代の交渉
- 有休消化の交渉
- 利用者自身のトラブルに対する交渉(会社からの借金、社宅の損害など)
※交渉ではなく、「取得したい」という意向を伝えること自体は可能。伝えた上での会社の判断に左右される。
当然、退職代行サービス事業者は罰を受けるわけにはいきませんので、退職代行を実施できる依頼とできない依頼を見極めています。
この見極めを間違いなく行うために、「弁護士に監修を依頼し、自身の代行業務に問題がないか」をチェックしている退職代行サービスがあるということです。
みなさん自身がトラブルに巻き込まれてしまわないためにも、最低限、弁護士が監修しているサービスを選ぶのが無難でしょう。
また、最近は法令に間違いなく適合するために、「労働組合」と提携して退職代行にあたるサービスが出てきています。
労働組合は弁護士資格は持たない代わりに団体交渉権を保有していますので、「退職日の調整」「未払い賃金の支払い要求」などを含めて、会社側との交渉が認められています。(交渉に応じない場合、会社側が違法となる)
紹介した中では、「退職代行Jobs」、「男の退職代行」の2サービスは労働組合が代行しますので安心して良いでしょう。
2.退職理由はなるべく具体的にしておく
漠然とした理由のまま退職代行サービスを利用すると、代行実施時に会社側から「もっと具体的な理由を聞きたい」や、「その退職理由では納得できない」と言われてしまうことにもなります。
そうなると、退職代行サービスの担当者としても、利用されるみなさんに再度確認を取らなければならなくなります。
必要以上に何度も連絡のやり取りが発生するのは、要らぬトラブルの元にもなります。
会社側としてはいきなり退職代行サービスから連絡が入り、予定していなかった退職手続きを急遽行わなければならないわけですからスムーズに事を進めたいはずです。
そのためにも、なるべく具体的な退職理由を退職代行サービスの担当者へ伝えておくべきということです。
担当者としてはあらゆる退職理由を見てきていますから、事細かな理由や辻褄合わせまでは考えなくても大丈夫です。不安な点は、申込後の相談の場で担当者に相談したら良いでしょう。
3.退職の手続きのために会社から依頼されたことは迅速に対応する
最後の注意点です。
意外かもしれませんが、会社側から要求されたことをすぐに対応せずに放置したことにより、その結果トラブルになるケースが多いのです。
退職代行を実施して、会社からも退職の承認が得られると、その後には最低限の事務手続きがあります。
代表的なところでは、貸与されているPCや携帯、入門証の返却といった貸与物や、退職者全員が書くような書類です。
このような依頼事項に対するミスのサポートにまで担当者も付き合ってはくれません。
みなさんが想像するより退職代行サービスへの申し込みは多いですし、担当者としては一つ一つ神経を尖らせて対応しているのです。
会社側が即日退職を了承していたとしても、実際の手続きが進んでいかず長引けば、懲戒解雇の対象となる可能性もあります。
懲戒解雇は後々の転職先でも悪影響が出る恐れがあるので、会社側から依頼されたことは期限のうちに早々に対応しましょう。
最後に|悩む皆さんへ
一見すると、退職代行を使うことは社会的にネガティブなイメージで捉えられがちです。
ですが、みなさんが抑圧されて悶々とした日々から脱出できるのはいずれにせよ素晴らしいことで、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という言葉がとても似合います。
今この悩んでいる時間や、少々後ろめたい退職の仕方に戸惑う気持ちも、ことが済んで次の仕事に就く時にはすっかり過去のことに思えるということです。
繰り返しになりますが、派遣・客先常駐エンジニアのみなさんにとって、退職するだけでも多くの引き留めや自社都合に振り回され、他の職種より険しい道であるのは間違いありません。
退職までの険しい道にうんざりして退職代行を利用する方は非常に多いので、自分を責めすぎず前向きに捉えてしまっても差し支えないはずです。
- 退職代行Jobs|法令遵守を徹底している安心感
- 男の退職代行|月額3,630円から依頼可能
- 退職代行クラウド エンマン|弁護士による退職代行
1.退職代行Jobs|法令順守を徹底している安心感

「退職代行Jobs」は、顧問弁護士監修で適法適正に厳格な、安心の退職代行サービスです。
労働組合とも連携しているため、もし退職日や有休消化に関して会社と交渉が必要になったとしても問題なく交渉可能で安心です。
24時間365日、即日即時対応可能なのが魅力。
料金は依頼者の雇用形態を問わず一律税込み29,800円で、料金は退職完了後に後払いすることも可能ということで信頼感があります。
2.男の退職代行|男性人気No1、月額3,630円から依頼可能
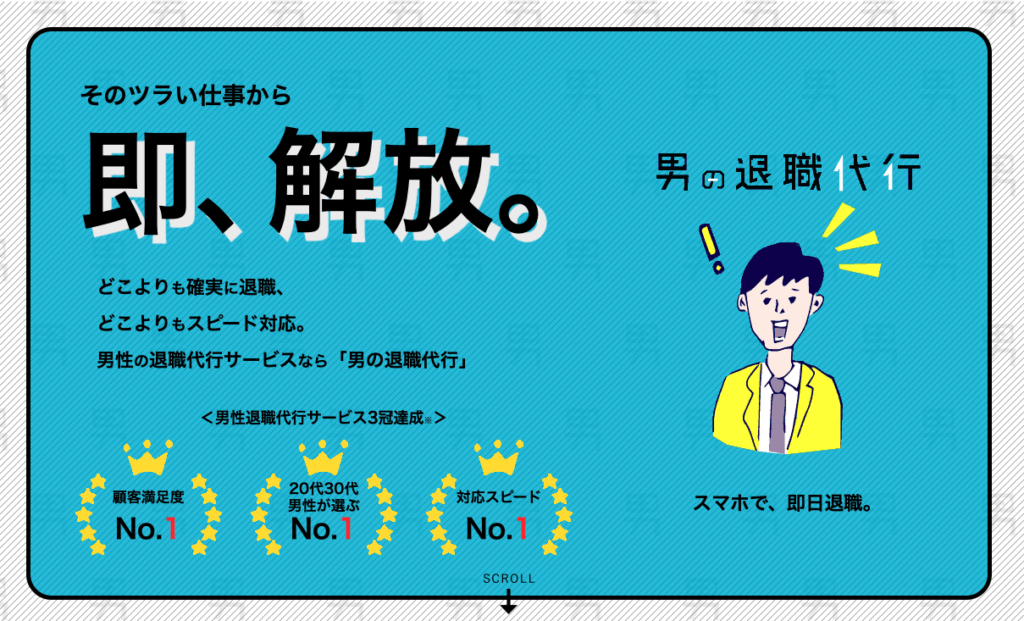
「男の退職代行」は、株式会社インクルが運営する男性向け退職代行サービスです
ユニークな名称のサービスですが、JRAA(日本退職代行協会)にて優良事業者であることを証明する「特級認定」を取得している、真面目な代行サービスです。
法的に認められた労働組合が退職代行サービスを行うため違法性の心配もなく、安心して依頼することができます。
通常料金は29,800円と相場並みですが、「月額3,630円で、1年間に2回まで利用可能なサブスク契約」という、非常に特徴的な料金プランがあります。
実質的には分割払いとして考えればいいので、新入社員や第二新卒のような経済的に厳しい方にはありがたいサービス形態でしょう。
3.退職代行クラウド エンマン|弁護士による退職代行

「退職クラウド”エンマン”」は、紹介している3サービス中で唯一、弁護士が代行して交渉してくれるサービスです。
信頼できる退職代行サービスでは弁護士が監修・指導しているものですが、エンマンについては弁護士自らが代行を請け負ってくれます。
万が一にも会社側が強固に拒んだり、本人との接触を図ろうとしてきた場合にも、弁護士自らが交渉を行なってくれているので安心感が違います。
ただし、料金は税込み55,000円と高めの設定なのが厳しい点です。
(追記:退職が多い時期ということもあり、期間限定キャンペーンで33,000円での依頼が可能とのこと)
炎上案件に首を突っ込んでいて絶対に直接話したくない方や、有休消化・給料支払いが確実に必要だという方には、安心感を買う意味でエンマンを選ぶとよいでしょう。退職代行」とは、簡単にいうと「辞めたい」会社に社員本人に代わって退職代行業者が退職の意思を伝えてくれるサービスのことです。