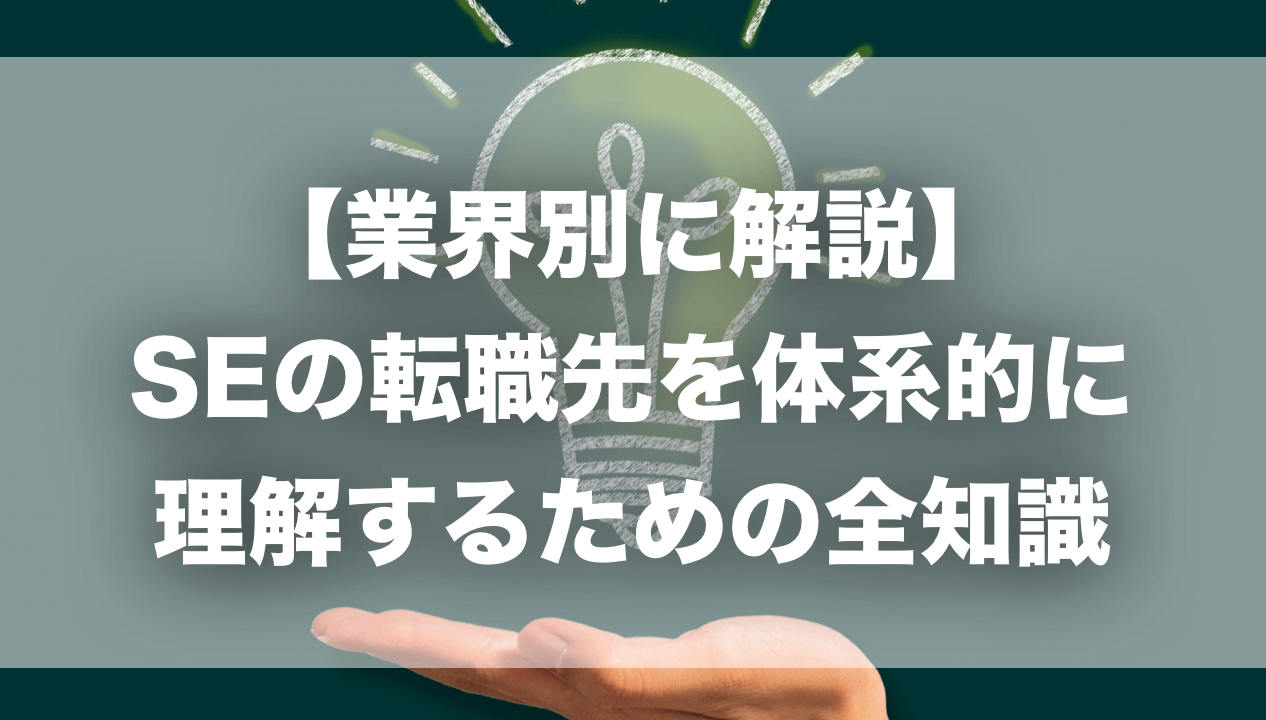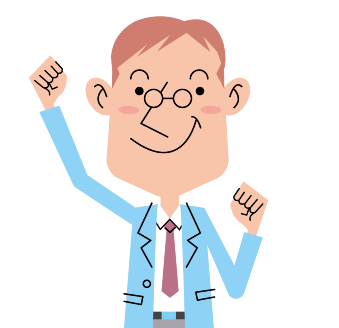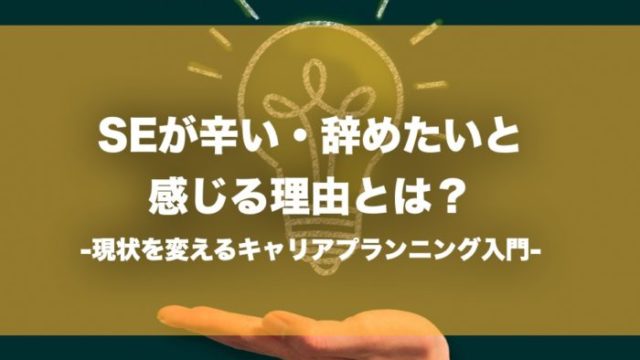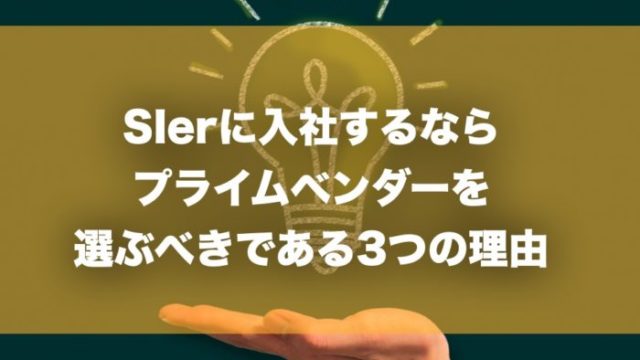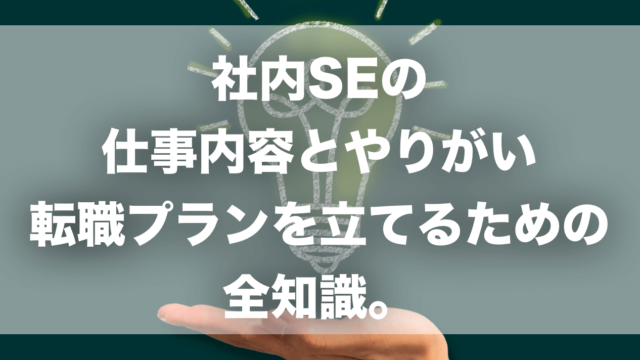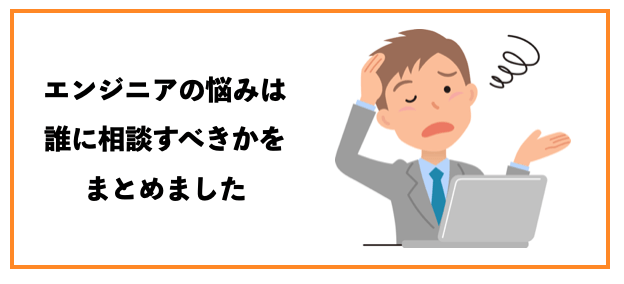このページでは、主にアプリケーション開発に従事するSEが、転職先として選ぶ可能性の高い業種に的を絞って解説します。
IT業界と一口に言ってもかなりの広さです。
特に、今回は転職先という意味合いですので、
それぞれの業界の特徴や身につく力、その先のキャリアなど、キャリアに関するポイントに絞って解説していきます。
まず大前提として、SEの方々が働く業界、そして転職先となりうるのは大別すると以下の5つに分けられます。
転職力をつけるために行うべき最初のステップは、IT業界を知ることにこそあると言えます。
これら5つの業界は、同じようで大きく違いますので特徴を掴んでいきましょう。
SEの転職先① ユーザー企業の「社内IT部門・社内SE」
長期的な視点で企業の情報化に携わることができる点が魅力です。
長期間にわたって特定の企業の情報化推進に貢献したいと考えるSEは多く、
社内IT(情報システム)部門の、いわゆる「社内SE」はエンジニアにとっては非常に人気の職種です。
何故ならば、結局SIerやITコンサルといった「ユーザー企業の外部」からの支援では、
「結局どれだけ頑張っても、外部には変わりない。」
「本当の満足感が得られない。」
こんな風に感じてしまう外部だからこその虚しさがあるからです。
ユーザー企業の社員しか感じられない「長期的な努力で企業が成長する」達成感があります。
社内IT部門・社内SEの3つの仕事内容、役割とは?
社内IT部門・社内SEの仕事内容と役割は、大きく3つに分けられます。
- システム企画(システム入れ替え、新規システム導入など)
- システム開発時のプロジェクト管理(実際に開発を担当するSIerとの窓口役)
- システム運用(今利用されているシステムの保守・運用、問い合わせ対応)
社内SEの仕事は広範囲に渡ります。
企画して、導入、その後のアフターケアまですべて行うわけですから、「自分で計画立てて行動する」能力が必要になります。
当サイト内の「社内SEの仕事内容とやりがい、転職プランを立てるための全知識。」では、さらに深掘りして社内SEの魅力、メリット・デメリット、転職するためのキャリア戦略を解説しています。
https://karitetour.com/jobchange/bunya/it-field/se-field/job-of-system-administrator/
SEの転職先② 従事している人数が最も多い「システムインテグレーター(SIer)」とは。
もともとSIerは、ハード・ソフト・ネットワークなどを別々に売っていた時代に、「システム開発を統合的に行う」という意味を込めて生まれた言葉です。
ですが、今では「企業の情報システム開発に携わる企業全般」を指すことが多くなっています。
SIerのエンジニアの職務内容
通常、SIerに入社した社員は、
「プログラマー(PG)→ SE → プロジェクトマネージャー(PM)」
という順序で職位を上げていきます。
職務内容1:プログラマー(PG)
プログラマーは、文字通りプログラム開発を担当し、原則としてすでに用意された仕様書(設計書)に基づきプログラミングを行う立場。
職務内容2:SE
SEの仕事はシステムの全体設計始まり、個別のプログラムの設計に至るまで、システム開発の仕様全般に携わる立場。
場合によっては、クライアント(システムを発注・利用するユーザー)からのヒアリングに基づき、業務要件をまとめたり、新たな業務プロセスを定義する役目を担うこともあります。
職務内容3:プロジェクトマネージャー(PM・プロマネ)
PMの仕事は、システム開発プロジェクト全体を統括することであり、以下の内容を統合的に管理する立場。
- 予算
- スケジュール
- 要員(社員、協力会社など)
- 外部ベンダー(ソフトやハードウェアのメーカー)
- システム仕様
管理する対象は多岐に渡ります。
もちろんクライアントとの最終的な窓口としても機能しなくてはなりません。
垂直的に分業しているSIerの業界構造
SI-erの業界は建設業界や自動車業界と同様に、複数の企業が垂直的に仕事を分業しています。
分業と言えば聞こえは良いのですが、要はプライムベンダーから二次請け、三次請けと仕事がどんどん下の層に降りていく構造です。
ですから、実際に現場で仕事に従事している人たちは、経済的にかなりタイトな状況で働かなくてはならないという現実が生まれています。
また、仕事の質も階層によって異なります。
要件定義や概要設計など、いわゆる上流工程とされる仕事のほとんどはプライムベンダーが受け持っていることが多く、
一方で、三次請けのSEは上流工程の仕事に就くチャンスが限られてしまっている状況です。
SIerでのSEのキャリアパスは増えつつある
SI-erでのSEのキャリアパスは「PG→SE→PM」という道を辿ることが一般的ですので、「専門職から管理職への流れ」を沿う形になります。
ただ、ある種のスペシャリストであるエンジニアの皆さんは、必ずしも管理職への昇格を願っているわけではないでしょう。
PMの激務を目の当たりにしてしまうと、「自分には無理だ」と思ってしまう方も多いと思います。
そういった背景から大手SI-erを始めとして、いわゆる上級の専門職である「アーキテクト」や「スペシャリスト」と呼ばれる立場が設定されている場合があります。
スペシャリストは読んで字の如く「専門家」です。
SEが昇進するためにはPMとして管理職になることが求められますが、「現場にいたい」「最新のテクノロジーを追求したい」という思いを持つみなさんを受け入れられる環境がある会社を選ぶことが望ましいです。
データベースや開発言語など特定の領域での専門性を高めていくことが求められ、それがキャリアアップに繋がるというわけです。
エンジニアの皆さんは本能的に「現場にいたい」、あるいは「最新のテクノロジーを追求したい」という思いを持っているはずです。
アーキテクトやスペシャリストを職種に追加するのは、そうした思考を組織になじむ形で取り込もうという動きと言えます。
SIerに将来性はあるのか
SI-erというのは、言ってみれば請負業者です。
企業から個別にシステム開発の依頼を受け、開発していくのです。
今後のSI-erの事業環境を考えると、この請負であるというビジネス構造に由来する2つのリスクが考えられます。
1つは、商談のタイミングで後れを取ってしまうリスクです。
最近はSI-erのところに見積依頼が入る時点で、既にユーザー企業側にコンサルティングファームが入り込んでいて、SI-erは単にシステム開発を受注するだけになってしまうことが起こっています。
これは、SI-erそのものがコンサルティングファームの下請けになってしまうことを意味します。
なぜこんなことが起こるかと言うと、商談のタイミングの問題に行きつきます。
これまでユーザー企業、つまりクライアントのニーズは「会計システムを導入したい」とか、「受発注処理を自動化したい」という「システム開発」が前提となっているものがほとんどでした。
ところが、最近の企業、特に経営者のニーズはもう少し上のレイヤーにあって、たとえば「会計基準をグローバル標準に合わせたい」とか「サプライチェーンのプロセスを再構築したい」というように、経営上、あるいは業務遂行上の課題解決に主眼が置かれています。
もちろん、一部のSI-erにはそうした経営課題を解決するだけのノウハウは存在するでしょう。
しかしながら企業側は「経営課題の解決なら、まずはコンサルティングファームに相談しよう」と考えるわけです。
そこで商談の初期段階でコンサルティングファームにだけ声がかかるというケースが生まれます。
これに対し大手SI-erは、自社の系列会社にコンサルティングファームをそろえたり、特定のコンサルティングファームと資本提携や業務提携をすることで、より初期の段階、言い換えれば上流から参入できるように体制を整えているのです。
(例:NECによるアビームコンサルティング買収、日立製作所による日立コンサルティング発足)
一方、コンサル機能を持たないSI-erは、今後プライムベンダーとしての活躍の場が少なくなっていくことが考えられます。
SEの転職先② 人気の「ITコンサルティングファーム」
ITコンサルタントとは、一言でいえば「ITを活用して企業の課題を解決する専門家」です。
経営戦略に沿ってIT戦略を策定し、システム開発の提案やシステムの最適化を通じて、企業の経営を助ける職種です。
ITコンサルタントの仕事は、企業のIT戦略の策定からシステムの見直し、新システム導入の提案、システムの最適化や動作検証まで多岐にわたります。
「ITコンサル」と「戦略コンサル」の違いとは
戦略コンサルが「企業の経営課題全般」に対応するのに対し、ITコンサルは「業務プロセス」の一部に着目したコンサルティングです。
1:戦略コンサルティングファーム
戦略コンサルティングファームは、企業の経営戦略や事業戦略策定のコンサルティングサービスを提供するサービスです。
つまり、こちらは技術職・エンジニアだけでなく、もっと広範に渡って活躍するような業務と言えます。
2:ITコンサルティングファーム
ITコンサルティングファームは、通称・業務系コンサルティングファームと呼ばれることもあります。
コンサルティングの対象として、サプライチェーンやCRMなどの業務プロセスの改革を主眼に置いていることから、「業務系」と呼ばれるようになりました。
同時に、業務プロセス改革の結論として情報システムの刷新が行われることが多く、情報システム導入のコンサルティングサービスを主たるメニューに据えていることから、ITコンサルティングファームとも呼ばれるわけです。
1990年代の半ば以降、ITコンサルティングファームは花形業種の仲間入りを果たし、相変わらず高い人気を誇っています。
それは給与水準の高さや、高度な専門知識を背景に企業幹部に向けた助言を行っているというイメージ、そしてそれらに裏打ちされたステイタスの高さなどから人気となっているのではないかと推測しています。
また、ほぼ完全な実力主義であることが、伝統的な日本企業に対するアンチテーゼとして人気を集めている側面もあります。
要はやればやっただけ見返りが期待できるという点です。
もう一つ、コンサルティングファームが人材輩出企業であるというイメージも、同業界の人気の一因かもしれません。
上場を果たしたベンチャー企業の創業者、あるいは企業幹部にはコンサルティングファーム出身者が少なくありません。
こうしたイメージから、引き続き高い人気を得ているのでしょう。
SEからITコンサルタントへの転身は可能?
よく転職希望者から、「SEからコンサルティングファームに転職できますか?」という質問を受けますが、応えは「イエス」です。
ただしコンサルファームと言っても、それが「戦略ファーム」の事を指している場合は少々難しいかも知れません。
ちなみに戦略ファームとは、企業の経営戦略や事業戦略立案に特化したコンサルティングファームの事を指します。
戦略ファームの代表的な企業としては、マッキンゼー、ボストン、ベインなどがあり、大手企業の経営企画部からの転職者が多いことが特徴です。
一方、ITコンサルの場合には、SE出身の人がたくさん働いています。
では、どんな人がITコンサルタントとして活躍できるのでしょうか?少し考えたいと思います。
それを考えるにあたり、まずSEとITコンサルタントの仕事の違いを見てみましょう。
本稿の冒頭でも多少触れましたが、 ITコンサルタントが扱うテーマは第一に「業務プロセス」です。
サプライチェーン改革やCRMの導入整備、最近では内部統制への対応など、企業活動のあらゆる側面において重要となる業務プロセスを、時代背景や企業を取り巻く環境に応じ最適化していくことがITコンサルタントの仕事です。
そして、その業務プロセス改革の1つの果実として情報システムの導入や再構築というテーマが浮上するのです。
システム化以降の流れはSI-erと同じですが、開発プロジェクトへの携わり方は異なることがあります。
SI-er同様、開発プロジェクトにメインプレイヤーとして参画することもありますが、ここ数年は開発プロジェクトにおける垂直分業が進んでいるため、ITコンサルタントは主にプロジェクト管理に専念するケースが増えてきています。
こうしたことから、ITコンサルタントの仕事をあえて定義すると
クライアントの経営課題を業務プロセスと言う観点から抽出し、
→あるべき業務プロセス像を定義し、
→新たな業務プロセスを構築し、
→新たな業務プロセスにもとづいてシステム化要件を定義し、
→当該業務プロセスをサポートする情報システム導入が円滑に行われるよう管理する。
ということになります。
これに対し、一般的なSEの仕事を定義してみると、
新たな業務プロセスに基づいてシステム化要件を定義し、
→システムの仕様設計を行い、
→仕様に基づいた情報システムを開発すると同時に、
→当該情報システム導入が円滑に行われるよう管理する。
と言うことになると思います。
つまりITコンサルとSEの最大の違いは
ITコンサルタントは「企業の経営課題解決」に対してコミットしているのに対し、
SEは「情報システム構築」にコミットしている
という点と言えます。
これを、私なりにもう少しかみ砕いてみると、
ITコンサルタントは「変えること」に責任を持ち、
SEは「組み立てること」に責任を持っているのではないかと考えます。
もう一つ例を挙げるとすれば、
「ITコンサルタントはクライアントにコミットし」
「SEは仕事にコミットしている」という違いもあります。
ITコンサルタントがクライアントに対して抱くコミットメントの意識はある種絶対的なところがあります。
「クライアントの成功のためなら、どんな努力も惜しまない」という姿勢は、全てのITコンサルタントに通じる姿勢です。
この違いを理解できるかどうかが、SEがITコンサルタントとして活躍出来るかのカギであると感じています。
何かを変えるというのは、大きな力を必要とします。
変化を嫌う抵抗勢力の存在もそうですし、何よりも新たな創造活動をすることは大きな労力をともないます。
しかも、そうした努力を自分のためでなく、常にクライアントのために提供するということを理解できれば、コンサルタントへの転身は十分可能でしょう。
そのためには、主体的な態度が何よりも求められます。
自らの意思と意見を持ち、自らが起点となって動くことがとても重要です。
スキルベースで言えばSAPやOracleEBS等のERPパッケージでの開発経験がある人は採用されやすい傾向にあります。
SCMやCRM、会計などの特定の業務システムで複数の設計経験があって、かつ、そうした業務についての知識がある人も好まれます。
それ以外でも、情報システムのアーキテクチャの設計や構築経験がある人は、テクノロジーコンサルタントとしての採用可能性が高まります。
花形であるITコンサルティングファームの行く末
ここ数年、大手ITコンサルティングファームは大きく業容を拡大しました。
アクセンチュアはまさにその典型で、最上流での経営コンサルティング、システム導入、運用と垂直的に事業基盤を整えました。
そうした状況を見ていると、今後のコンサルティングファームは二極化していくのではないかと想像しています。
1つは大手コンサルティングファームの総合力強化と事業規模の更なる進行、そしてもう1つはより特定の業界や業務領域の専門性を高めたブティックファームの台頭です。
大手コンサルティングファームは、最上流でのクライアントとのリレーションをてこに、経営とITに関わる様々なサービスメニューを整備し、さらに企業活動に深く浸透していくことでしょう。
そうした流れの先で言うと、もはやコンサルティングファームではなく、巨大なITサービス会社と呼ばれるにようになるかも知れません。
一方で、そうした総合的なサービスに飽き足らない企業にとって、特定の業務プロセスや業務経験が豊富な小規模のコンサルティングファームの需要が高まっていることも事実です。
例えば、小売業に特化したコンサル、金融業界に特化したITコンサルなどが既に存在し活躍しています。
SEの転職先③ 寡占化が進む「ソフトウェアベンダー(ソフトハウス)」
ソフトウェアベンダーとは、パッケージソフトやクラウドシステムなどを開発・販売する企業を指します。(ソフトハウスとも呼びます)
また外資系のIT関連メーカーの製品を日本で販売する企業も、ソフトウェアベンダーと呼ばれることが多いです。
ソフトウェアベンダーの厳しい市場環境
これにはベンダー業界の熾烈なシェア争い、そして一部の企業のみが生き残っていくような熾烈なマーケットであることが背景にあります。
かつてはビジュアル開発ツールのベンダーやERPパッケージのベンダーなど、数多の企業がひしめいていたソフトウェアベンダー市場ですが、現状は寡占化が進み熾烈なシェア争いが繰り広げられています。
ソフトウェアというもの自体、デファクトスタンダードへの流れが非常に強く働く業界であり、カテゴリーごとに大手2〜3社のみが生き残れると言った具合です。
実際に、強大な力を持つ一部の大手ベンダーが小規模ベンダーを買収してさらに巨大化していくと言った動きも続いています。
海外勢だけでなく日本発で急成長を遂げたワークスアプリケーションズやソフトブレーンと言った大手企業もあるものの、現時点では転職先の選択肢が少ない状況ではあります。
ソフトウェアベンダーならではの強みと弱み
自社のプロダクトを持つということは、請負でシステム開発をするとき以上に、社内にノウハウが蓄積され、ソフトウェアの品質や機能強化につながるという利点があります。
SIerのように請負でシステム開発する場合、どんなにクオリティの高いソフトウェアをを納入しようとも、請負金額が回収しうる売り上げの上限です。
一方で、パッケージソフトは開発初期のオーバーヘッド(コスト負担)はあるものの、初期コストを回収した後は全て利益貢献するわけです。
一時期よく言われた「収穫逓増の法則」が当てはまる業界として、製品が売れれば売れるほど、その製造コストが劇的に下がるというモデルであることもこの業界の強さです。
一方、ソフトウェアベンダーの弱みは、自社でプロダクトを持ってしまっている点です。
要は自社でプロダクトを持っていることが強みであり、同時に弱みでもあるわけです。
先ほども触れた通り、ソフトウェア開発は莫大な初期投資を擁するビジネスです。
そのコスト負担を回収するだけの売り上げを見込まねばならず、かつまた協業製品との機能強化の競争に打ち勝つために、たゆまぬ改良が必要となります。
資金力に勝る企業にビジネス機会が集中するのも、まさにこうした事業構造に由来するのかもしれません。
ソフトウェアベンダーでは、ハードながら最先端の技術に触れられる喜びを感じられる
1つのソフトウェアプロダクトをリリースするには、たくさんのエンジニアが数年の歳月をかけて開発していきます。
製品として出荷するわけですから、細部にいたるまで仕様を細かく定義し、繰り返しテストが行われます。
また、リリースと同時に陳腐化が始まりますし、機能修正をすることも容易でないことから、常に最先端の技術と機能を盛り込むことが求められます。
したがって、ソフトウェアプロダクトの開発はとてもハードなのですが、大きなやりがいを実感できる仕事であると言えます。
ただ、現在マーケットで主流となっているのは欧米のソフトウェアベンダーのプロダクトですので、メジャーなソフトウェアベンダーへの転職を希望する場合、必然的に外資系企業を選ばなくてはならない可能性があります。
とは言え、外資系ソフトウェアベンダーの日本法人におけるエンジニアの大きな役割はローカライゼーションなので、開発の最前線でノウハウを得たいという人には物足りないかもしれません。
ただ、先ほども紹介した通り、国内でも有力なソフトウェアメーカーが少しずつ力をつけているので、そうした企業ではやりがいを持って仕事するチャンスがまだまだあります。
オープンソースやクラウドコンピューティングの影響を受け、役割の変化が求められる
ソフトウェアビジネスは、ここ数年で激変の兆しを見せています。
かつては、パッケージ製品を購入し、自社のシステム環境にセットアップして利用する形態が主流でした。
ソフトウェアのソースコードは公開されず、サードパーティのベンダーが大手ソフトウェアベンダーのソフトウェアと連携するソフトを開発するのにも一苦労でした。
ところが、インターネットの爆発的普及によるネットワーク環境の整備が進み、オープンソースの流れが加速したことで、ソフトウェア開発や配布、あるいは利用環境が変化しつつあります。
まず、ソフトウェア開発の変化については、ソースコードを公開して機能ごとに利用できたり、システム間の連携が行いやすい環境が整ったことで、ソフトウェア開発元の先行者利益が薄れています。
視点を変えれば、たとえ限定的な機能であっても、爆発的なニーズを見込めるプロダクトにも、陽の目を見るチャンスが生まれたと言えます。
配布、利用についてはASPの流れを受けたクラウドコンピューティングという考え方が急速に広まったのはいうもがなです。
従来、ソフトウェアを含むシステム資産は所有して利用するものでしたが、現在は外部から提供される機能を利用することが主流になってきています。
となると、かつてハードウェアベンダーが直面したようなサービス事業への流れが、ソフトウェアベンダーにも広まっていくことが考えられます。
単にソフトを開発するだけでなく、そのソフトウェアを軸にユーザーが便利に利用できるような環境を提供するまでがソフトウェアベンダーの役割となってきています。
SEの転職先④ あらゆる意味で新しい「WEB系企業」
WEB系とはインターネットを使う「Webシステム」のことを指しており、そこで働くWEBエンジニアはWEBサイトやWEBアプリの開発・運用などを行う職業のことを指します。
SEの場合はあくまで企業内で利用される社内システムの設計構築を行うのに対し、
WEBエンジニアの場合は一般ユーザーが利用者であるシステムを担うと思えば良いでしょう。
業界の特徴として、WEB系企業はSIer等と比較すると若い業界であり、働いている人たちも比較的若いのが特徴です。
若いといっても、大手企業が今や乱立している状況ではありますのですでに一般的な業界ではあります。
WEB系企業の具体例:
ドワンゴ、カカクコム、クックパッド、ヤフー、一休、ぐるなび、楽天、等。
WEBエンジニアはユーザー目線でのシステム作りをしている
企業向けの情報システムの場合、それが重要な機能であったとしても、想定されるユーザーは数人ということも少なくありません。
業務アプリケーションなわけですから、たとえば経費精算のような全社員が使うような機能ではない限り、当該業務に関わりのある人だけがシステムを利用するのは当然なのです。
これに対しネット系のシステムの場合、そもそも一般のユーザーに向けてシステム(WEB)を公開する前提で開発しています。
個人情報や決済条件などの入力も必要ですので、セキュリティやクリティカル性という意味では企業の情報システムに引けを取らない信頼性が求められます。
その意味では、技術的に優れたSEがたくさん集まっていることも特徴の一つです。
特に、オープンソース系の開発言語に長けたSEが沢山います。
WEBエンジニアの特徴と身につくスキル
WEB系のSEと話をしてみると、「システム開発」の視点と「サービス開発」の視点の2つを持っているのを強く感じます。
つまり、「どんなサービスがあるとユーザーにウケるのか」とか、
「どんな画面にすればユーザーが利用しやすいのか」といった視点です。
業務系システムの開発となると、ついついユーザーの顔が見えなくなってしまい、システム開発そのものが目的となってしまいがちです。
が、その点でネット系のSEは優れているなと感じています。
WEB系エンジニアの仕事のやりがい、SEとの違いは?
WEB系企業におけるエンジニアのやりがいは、例として2つ挙げられます。
- ユーザーを意識したシステム作りができること
- 技術的なスキルが広範囲にわたって身につきやすいこと
それぞれ見ていきましょう。
WEBエンジニアのやりがい① ユーザーを意識したシステム作りができること
WEBエンジニアのやりがいの1つは、常にユーザーの立場・目線を意識したシステム作りができることです。
WEB系企業で開発するシステムは、そのほとんどが不特定多数のユーザーの利用を想定しています。
ですので、ユーザーの反応を常にダイレクトに感じながら仕事ができるという良さがあります。
一方で、SIerのSEとの違いを見てみますと、
SEのよくある悩み:
「自分の作ったシステムがどのようにユーザーに使われているのかわからない。」
「ユーザーにどんな利便性を提供できたかわからない。」
と、嘆くケースがあり非常に対照的であると言えます。
WEBエンジニアのやりがい② 技術的なスキルが広範囲にわたって身につきやすいこと
WEBエンジニアのやりがい2つ目は、技術的なスキルが広範囲にわたって身につきやすいことです。
従来の業務系システムの開発において、アプリケーションエンジニアが最低限知っておかなくてはならないのは開発言語についてでした。
しかし、WEBエンジニアの場合、開発言語だけでなく、サーバーやネットワークなどを含めたシステム環境を意識した開発が求められます。
これはWEBサイトの場合、短時間に不特定多数のアクセスが集中する可能性があるためです。
そうしたことから、単にプログラム開発ができるという以上に、システム環境全般に対する理解が深まるようです。
一方で、WEB系のシステム開発においては、日々改善を続けていくことが少なくありませんので、常に追い立てられているような感覚に陥ることがあるようです。
緊張感が続くという意味では、やりがいがあるとも言えますし、それがストレスにつながる可能性も否定できません。